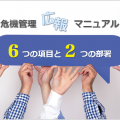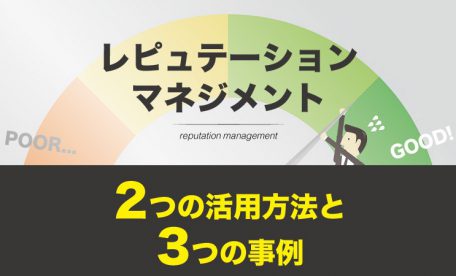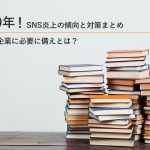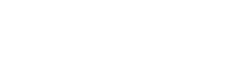本記事では、「危機管理広報とは何なのか?」まとめました。企業として必要な準備と正しい危機対応について「SNSから発生する危機」にも着目しながら解説します。
危機管理広報という言葉はよく耳にすることがあっても、具体的にどのような活動や施策のことを指すのか、あまりピンとこない方も多いと思います。今回はそのような方に向けて、特にSNSから発生する危機に注目して「危機管理広報とは何なのか」まとめました。ぜひ今後の社内体制の構築や、対策のご参考にしていただければと思います。
「【もしもの時に使える】謝罪エラーチェックシート」をダウンロードする
危機管理広報とは?
危機管理広報とは、企業にとっての危機的状況が発生したときに、被害や損失を最小限にとどめて収束させるための一連の活動のことを指します。
一般的な広報活動が企業のブランディングなどポジティブなものであるのに対して、危機管理広報は企業を守るための活動といえるでしょう。

SNSの普及による変化
SNSをはじめとするソーシャルメディアが急激に普及したことで、企業が直面する危機も変化しました。情報の拡散力が強くなり、そのスピードも大幅に速くなったため企業の対応もより早く、的確なものが求められるようになっています。
想定される危機とは?
不祥事や事故
リアルタイムで起こってしまった不祥事はもちろん、過去の不祥事やコンプライアンス違反が掘り起こされることも少なくありません。組織として起こしてしまった不祥事や事故から、従業員個人の不適切な言動まで発生源は幅広いため、それぞれをリスクとしてしっかりと把握しておく必要があります。
災害による危機
大規模な自然災害などが発生してしまった際の危機についても備えておく必要があります。発生した後に「想定外だった」という見解を発表したことで企業としての信頼を大きく失ってしまう事例は少なくありません。自社がおかれた環境や日常業務を鑑みて、最悪の事態を想定した対策を行いましょう。
ネット炎上
SNSが普及してからは危機の発生源はインターネット上にも広がりました。企業としての不適切な情報発信がきっかけとなるだけではなく、関係者による内部告発がネット上で行われたり、不祥事や事件などがネット炎上を介してさらに大きな危機へと発展したりすることがあります。
発生前に必要な準備

危機管理広報の基本は大きく2つに分けられ、その1つ目が日常的な「準備」です。いつ発生するか分からない危機に備えて最悪の状況を想定した準備を行っておくことが重要になります。主に準備が必要なのは次の3つについてです。
社内体制の構築とマニュアル作成
まずは危機発生時に備えるための社内体制構築を行いましょう。あわせて危機発生時の初動対応から収束までのフローをまとめたマニュアルを作成することで、有事の際の混乱や対応ミス、遅れを防ぐことができます。
【社内体制・マニュアル策定時の例】
・危機発生時の統括責任者を決める
・各対応の担当部署を決める
・危機発生時の社内への伝達経路を策定する
・メディアをはじめとする社外対応の一元化
メディアトレーニング
どれだけ入念な準備をしていても、メディア対応の方法を誤ってしまえばすべて水の泡になりかねません。そのようなことがないよう、正しいメディア対応を行うために必要なのがメディアトレーニングになります。
メディアトレーニングでは、実際の危機発生を想定したシナリオを作成し、記者会見の予行練習や講義を行うものが一般的です。このトレーニングを行うことで、収束までの時間を最小限に抑える、ネット炎上への飛び火を防ぐなどの効果が期待できます。
ネット情報のモニタリング
素早く危機発生を把握するためには、ネット上の情報をモニタリングすることが有効です。SNS上への内部告発や従業員の不適切な言動、企業に関する誤った情報など、ネット上以外ではリアルタイムでの把握が難しい事象も多くあります。それらの情報がネットで拡散される前に初動対応を行うことが収束を早めるカギとなるため、日ごろから自社にまつわる情報を把握するためのモニタリング体制を整えておきましょう。
危機発生後の対応

危機管理広報2つ目の基本は、危機発生時の実際の対応についてです。初動対応によってその後の事態収束までの期間が大きく異なるため、迅速かつ正しい対応を行う必要があります。
メディア対応
企業の見解はメディアを介して、消費者やユーザー、世間に伝わる部分が多いです。そのため、その対応を誤ると世間に大きな誤解や不信感を与えさらなる企業イメージ、ブランドの低下につながってしまうかもしれません。以下のようなポイントに注意をして、誠実な対応を行いましょう。
● 情報の隠蔽、責任転嫁をしない
● 世間や消費者目線での対応を心がける
● 対応に一貫性を持たせる
● 高圧的、上から目線にならないように気を付ける
● 法的問題の有無に論点をすり替えない
Web・SNSの対策
ネガティブな話題がネット上にあがっているときは、誹謗中傷やデマ情報も広まりやすいです。もちろん情報の隠蔽はしてはならないですが、虚偽の情報に関してはきちんと把握をして対策を行う必要があります。「1つくらいデマがあっても仕方がない」と放置してしまうと、情報が独り歩きして思わぬ損失へとつながる恐れもあるので注意しましょう。
すばやく的確な危機対応を
危機発生後、どのような対応をするかでその後の収束までのスピードや企業活動への影響に大きな差が生まれます。日頃から準備を行い、万が一の危機発生時に正しい対応ができるように備えましょう。
レピュ研を運営するジールコミュニケーションズでは、メディアトレーニングやWebモニタリングサービスなど、企業の危機管理にまつわるサービスをご提供しております。ぜひ貴社の危機管理広報の一環としてお役立ていただければと思います。